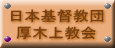
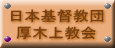
1.電動アシスト自転車
最近初めて電動アシスト自転車というものを乗りました。みなさんももうすでにお乗りになったことがあるかもしれません。普通に自転車をこぐと、まるで坂道を下っているかのようにすいすいと前に進むのです。なにせ初めて乗ったものですから、その快適さにびっくりしました。上り坂でも苦労せず進むことができます。便利な自転車ができたものだと思いました。
さて、なんで受難週にこんな話をするんだろうということですが、教会でも、イエス様のことを電動アシスト自転車のように便利なものとして考えるむきがあるのではないかと思うからです。人間が生きておりますと様々な困難があります。こんな時にいつも共にいてくださる神様やイエス様が助けてくださる、ということがよく聞かれます。いつも共にいてくださる神様やイエス様が助けてくださるという考えはとても素敵ですし、実際わたしたちの支えになっています。しかし、わたしは敢えてこのことに反対を申し上げようと考えています。なぜならば、イエス・キリストの恵みは、自分中心から離れて神様中心に生きるときにこそ与えられるものです。自分に都合いい神様を求めたり、あるいは神様を電動アシスト自転車程度に考えたりしていると、その程度の恵みしかないのではないでしょうか。
2.十字架への道
そのことは聖書の中にも見られます。イエス様がエルサレムに入場される前、はじめてご自分が十字架にかけられ三日目に復活すると弟子たちに打ち明けられた時に、ペトロはイエス様に「そんなことはあってはなりません。」といさめた、とあります。ペトロ自身はイエス様をメシアと告白していましたが、そのメシアとは、ユダヤ人をローマの支配から救う英雄としてのメシアであったようです。また、イエス様がエルサレムに入場されたときに人々が「ダビデの子にホサナ」といって大歓迎をした様子が描かれていますが、この人々にとっての「ダビデの子」とは、自分たちを解放してくれる英雄であったのです。それはすなわち人々も、そして弟子たちすらイエス様のことを理解していなかった。自分たちにとって便利な、いわゆる「電動アシスト自転車」のように考えていたのです。人間がイエス様のことを理解せず、自分に都合の良いものと考えてしまうこと、これは神様のお気持ちを少しもわからないということです。このことは人間の持つ罪からおこることですが、これに対して神様は断固として、はっきりと「ノー」と言われたのです。これがまさにわたしたちが今日読みましたイエス様のご受難の出来事だったのです。
3.聖書のテキストから
受難週のテキストは、マタイによる福音書の27章の後半です。舞台はエルサレム、時は過越しの祭の最中です。イエス様が裁判にかけられた後、十字架にかけられる場面です。優しいイエス様、平和を愛するイエス様、病をいやす奇跡をおこなうイエス様、こんな素晴らしいイエス様が皆から罵倒され、捨てられ、みじめな姿で殺されていくのです。ここに、人間の罪の深さをみるのです。
さて、はりつけにされる罪人は、総督官邸からされこうべという意味の「ゴルゴタの丘」まで、十字架の横木を背負わされることになっていました。イエス様は、むち打たれて体力の限界に来ていたのでしょう。前に進むことができなくなってしましました。そこで、ローマの兵隊達はそこに居合わせたキレネ人シモンに十字架を担がせました。この「シモン」という人物は聖書で初めて登場する人で、ほんの通りすがりの人です。しかし、マタイ、マルコ、ルカ福音書にも登場する人物です。キレネ人シモンは外国に住むユダヤ人です。マルコ福音書にはアレクサンドロとルフォスの父で、田舎から出てきて通りかかったとあります。キレネというのは北アフリカにあった、現在のリビアのトリポリの近くの町です。当時、アレキサンドリアと並んで、ユダヤ人の多い町であったと言われています。エルサレムから決して近い所ではありません。北アフリカのキレネ〜エルサレム間は、約1,500kmの距離です。この距離は福島と熊本の距離です。きっと何度も船を乗り継ぎながら来たのでしょう。ローマ帝国支配の国々に散らされていたユダヤ人にとっては、生涯に一度はエルサレムに巡礼することが夢でした。きっとこのシモンも、喜び勇んで参加した過ぎ越しの祭りでエルサレムに来ていたのだろうと思います。そこでちょうどイエス様のゴルゴタへの行進にでくわすのです。
4.キリストの十字架を担うということ
さて、皆さんはヴィア・ドロローサという言葉をご存知でしょうか。ヴィア・ドロローサとは、悲しみの道という意味です。イエス様が死刑の判決を受け、茨の冠をかぶせられ、十字架を背負って歩いた道を言います。10年前に私がエルサレムに訪問したときに、この道を見学しました。旧市街イスラム教徒地区からキリスト教徒地区へと続くおよそ1キロの道です。ヴィア・ドロローサには、聖書の記述や伝承に従って、14留(14ステーション)が指定されています。
ヴィア・ドロローサの出発点はローマ総督ピラトの官邸、終着点はゴルゴダの丘です。ゴルゴダの丘とされる場所には、現在、聖墳墓教会があります。
エルサレムに巡礼するクリスチャンは、このヴィア・ドロローサの道をたどりながら、イエス様の苦難の道を思い起こすのです。
5.神様の苦しみをしることは、愛を知るということ。
このヴィア・ドロローサの第5ステーションで、イエス様の十字架を背負わされたとされておりますシモンは、たまたまイエス様と出会いました。このシモンがその時どのように感じ、何を思ったかということの記述はありません。とんだことになったと思ったかもしれませんし、十字架が重くて苦しいと思ったかも知れません。シモンはたまたま田舎からでてきて、罪人の処刑の場面にでくわしてしまい、その十字架を担いで歩くという、とばっちりを食ってしまうのです。聖書の記事はそれだけです。シモンのこれまでの人生や、その後の人生の言及もありません。
しかし、このシモンの記事を読むたびに人ごととは思えないのです。たまたまイエス様に出会ってしまった。イエス様は処刑場に向かわされていましたが、死刑になるような悪い人にはみえない。しかし、文句も言わず、ただみずから歩むべき道を歯をくいしばって進もうとしている。そこには名誉も称賛もなく、ただみじめに捨てられた人間の姿だけがあったのです。その時シモンにはイエス様の目の中に、人間を必死で赦そうとする神様の愛の光が見えたのではないか、とわたしは想像しています。そしてシモンは、イエス様の十字架を担がされてその重さを経験しました。そして、その苦しみは人間を赦す愛の故の苦しみでしたから、神の愛の深さ、大きさを自分の体をとおして知ることができたのではないでしょうか。シモンに関しての伝説が生まれたのも、わたしのように想像した先達がたくさんいたからではないかと思います。その伝説は、シモンはこの後、敬虔なクリスチャンとなって初代教会を支える人物となったということです。
6.愛の大きさは罪の大きさ
シモンは、このことをきっかけに、神様の愛を知ることができたことを想像してみました。神様の愛を知るという事は、イエス様の十字架の重さを知るという事だと言えます。そして、その十字架の重さはわたしたちの罪の重さである、ということです。イザヤ書53章の「苦難の僕」の姿はイエス様の十字架によって成就されたと言われます。この一部をお読みします。
彼が担ったのはわたしたちの病
彼が追ったのはわたしたちの痛みであったのに
わたしたちは思っていた
神の手にかかり、打たれたから
彼は苦しんでいるのだ、と。
彼が刺し貫かれたのは
わたしたちの背きのためであり
彼が打ち砕かれたのは
わたしたちの咎のためであった。
彼の受けた懲らしめによってわたしたちに平和が与えられ
彼の受けた傷によって、わたしたちはいやされた。(イザ53:4-5)
わたしたちは自分の罪というものに気づかないで生きています。また、そのことを言われても理解できません。しかし、キレネ人シモンはイエス様の十字架の重さを通してそのことに気づいてしまったのです。十字架の重さを知るというのはイエス様の愛の深さを知るということであり、同時に自らの罪の深さを知るということです。受難週は、日頃神様を都合の良いものと考えていることをあらため、自分の罪に向き合う時でもあります。そして、その罪の大きさを知ることはすなわち恵みの大きさを知ることでもあります。
「神の苦しみ」にあずかることのできる幸いを感謝し、私達を救うために、担われた主の十字架をおぼえつつ、この受難週をすごしてまいりたいと思います。
天の神様
本日もみ言葉をありがとうございます。聖霊の力によって、この受難週を十字架をみあげつつふさわしい歩みができますようお導きください。