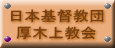
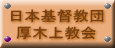
1.「復活」とは
さて、キリスト教は「復活」の宗教である、と言っていいほど、「復活」は信仰の中でも最も重要なことです。「イースター」と言えば、クリスマスよりも歴史の古い教会の祝祭です。ところが、この「復活」のことがどうもピンとこない、クリスチャンでない人はもちろんのこと、クリスチャンであっても、どうもよくわからない、というのが本当のところではないかと思うのです。初めて教会ができたころの信徒たちもよくわからなかったようです。パウロは、コリントの信徒への手紙一15章でキリストの復活について説明しています。
兄弟たち、わたしがあなたがたに告げ知らせた福音を、ここでもう一度知らせます。これは、あなたがたが受け入れ、生活のよりどころとしている福音にほかなりません。どんな言葉でわたしが福音を告げ知らせたか、しっかり覚えていれば、あなたがたはこの福音によって救われます。さもないと、あなたがたが信じたこと自体が、無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととしてわたしがあなたがたに伝えたのは、わたしも受けたものです。すなわち、キリストが、聖書に書いてあるとおりわたしたちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また、聖書に書いてあるとおり三日目に復活したこと、ケファに現れ、その後十二人に現れたことです。(1~5節)
パウロはコリントの教会の信徒に、福音とはわたしたちの罪のためにキリストが死なれたこと、そして三日目に復活したことだと断言しています。そして、このことを忘れてしまっては信じていること自体が無駄になってしまうというのです。これほどキリストの死と復活は重要なことだというのです。早い時期にカトリックと分裂した東方教会は復活のことをことさら重んじています。まさに「復活宗教」といってもいいほどです。わたしは神学生時代に四谷のニコライ堂の通常の礼拝に出席させていただきました。2~3時間という礼拝の長さもさることながら、この礼拝中出席者はずっと立ち続けているのです。椅子がいくつか用意されているのですがお年寄りも座る方はおりませんでした。わたしは礼拝の途中から足が痛みだし、そのことで頭がいっぱいになるほどでした。
その礼拝後、ニコライ堂の司祭と対談をしました。そのときに真っ先に「どうしてずっと立っているんですか」と尋ねました。すると司祭は、「礼拝ではキリストの復活を覚えてずっと立ち続けるのです。」と答えられました。「復活する」の原語は、「立ち上がらされる」という言葉です。神様によって立ち上がらされたキリストをおぼえて、礼拝中は立ち続けているのです。また、イースターの時は一晩中立ち続けて礼拝を持つというのですから驚きです。
しかしこのことを逆に考えると、復活は、このくらいしないと忘れてしまうということではないか、とわたしは思うようになりました。毎週2~3時間も礼拝で立ち続けて、体に刻み続けなければ忘れてしまうかもしれない。それほど復活はわたしたちに定着するのが難しいことなのだと言えるのではないでしょうか。パウロが手紙で書いている時代は、イエス様が無くなられてから20年ほどしか経っていない時代です。今でいえば平成の頃の事柄です。イエス様の記憶もまだ新しい時です。しかし、この時すでに、忘れてしまう人が多くいたということです。それほど復活の出来事は人々に定着するのが難しいことだったのです。
2.新しい命
はじめにもうしあげたのは「復活」はキリスト教のなかでも最も重要なことであるということでした。次にどうして「復活」が重要であるかを申し上げたいと思います。パウロはローマの信徒への手紙でこう言っています。
それともあなたがたは知らないのですか。キリスト・イエスに結ばれるために洗礼を受けたわたしたちが皆、またその死にあずかるために洗礼を受けたことを。わたしたちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死にあずかるものとなりました。それは、キリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、わたしたちも新しい命に生きるためなのです。(6章3~4節)
つまり、わたしたちもキリストの復活にあずかって、新しい命に生きることができる、ということをパウロは言っているのです。イエス様にならって倫理的な生き方をしましょう、というような次元のことではありません。わたしたちはいったん死に、今生きているのはわたしたちの命ではなくてキリストの命だというのです。これはわたしたちにとって大転換です。そしてこの大転換があるからこそ、「復活」はわたしたちにとって福音となるのです。
3.マグダラのマリア
さて、それでは本日のテキストになっているヨハネによる福音書20章をみてまいりましょう。これは復活の朝の出来事です。日曜の朝早くマグダラのマリアがイエス様の墓に行くと、墓の入り口を塞いでいた石がとりのけてあるのを発見します。そこで、ペトロともう一人の弟子(おそらくヨハネ)に伝え、3人で墓に行ってみると、もぬけの空だった。その後マリアが泣きながら墓の中を見ると二人の天使がおり、マリアは事情を話すのですが、後ろを振り向くとイエス様が立っており「どうして泣いているのか」と尋ねるのです。マリアはイエス様とは気づきませんでしたが、「マリア」という呼びかけでそのひとがイエス様だと気が付きました。そして「ラボニ」と呼びかけました。この時イエス様はこう言われます。
「わたしにすがりつくのはよしなさい。」
ここでわたしにすがりつくのはよしなさい。という言葉が何を意味しているのでしょうか。新しい聖書である聖書協会訳聖書では、「わたしに触れてはいけない」と訳されています。もとのギリシャ語は、「さわる」とか「しがみつく」という言葉ですから、このように訳されているのでしょう。これは、十字架上でイエス様が死んで悲しみに沈んでいたマリアが復活したイエス様を見たときに大感激し、もう離すまいとイエス様にしがみついたのでしょう。地上においてのイエス様とマリアとの関係がずっと続くことを、彼女が願ったのは当然のことです。しかし、イエス様が地上の生活を終え、天の父のところに戻っていくことは神様の計画です。神様と人間との関係が修復され、人間に救いがもたらされるのです。マリアはもう人間的な感情に流されてイエス様を求めることはできません。復活のイエス様に出会い、彼女も新しい命に生きなければならないのです。その後、マリアの「主を見ました」という報告をきっかけに、弟子たちが復活のイエスに出会っていくことになります。その後のマリアの足取りは聖書でおっていくことはできません。しかしながら、ある研究者はこのマリアは、教会の指導者となっていったと考えています。いずれにせよ、彼女がイエス・キリストの復活による新しい命に生きた第一人者だということができるのではないでしょうか。
4.結
本日は「復活」はキリスト教信仰の中心となる重要なことだと話してまいりましたが、わたしたちが今もっとも着目しなければならないのは、この事柄が歴史的に、あるいは観念的に(思想的に)重要なことであるということではありません。そうではなくて、今、ここでわたしたち自身におこっているからこそ重要だということです。イエス・キリストの復活によってわたしたちが今、キリストの新しい命にあずかっている。今までは自分の目で見ていたものを、キリストの目をもって見るようになるのです。目に映るものひとつひとつが新鮮で、いとおしいものになるのです。すべての存在の意味が転換します。これは、わたしたちは紛れもなく神様の恵みのうちに生かされていることを知ることなのです。このことに感謝して今年のイースターを喜びつつ迎えたいと思うのです。
天の神様
わたしたちにイースターの喜びを与えてくださり感謝します。キリストの十字架の死と復活は、わたしたちを新しい命に与えました。このことをわたしたちが生き生きと感じ、神様の愛に応える歩みができますよう導いてください。悩みと悲しみに満ちた世界に生きるわたしたちですが、人間の思いを超越した神様の愛がわたしたちに注がれていることを知ることができますように。そしてわたしたちをその愛で満たして希望を与えてくださいますように。