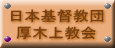
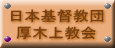
1.聖書の背景
さて、今日のテキストはヨハネによる福音書11章17節からです。マリアとマルタとラザロの3人兄弟は、エルサレムから3キロほどのベタニアという町に住んでいました。この3人はイエス様と親交があったようです。ある時、ラザロが病気になったという知らせがイエス様のもとに届きます。その時、イエス様は命を狙うユダヤ人たちから逃れて、ヨルダン川の東側に退去していました。命の危険を冒してユダヤに戻ることにします。しかし、なぜかイエス様は知らせを受けてからさらに2日間そこに滞在されてからベタニアに向かい、到着したのはラザロが死んでから既に4日が経ってしまっていました。
当時のユダヤの一般通念では、魂は死体の中に再び入ることを願って墓のなかの死体の周りを三日間さまようとされていました。しかし三日の後、魂が遺体の顔の色が変化したことを見届けると、永遠にその死体を離れるのだと考えました。したがって、死んでから4日経てば、その死が決定的になったのです。恐らくその時代、人が仮死状態になってもしばらくの間は、蘇生することがあったのでしょう。しかし、4日もたつとそれもあり得ないことでした。
2.マルタとイエス様
そして、イエス様に会ったマルタはこう言います、「主よ、もしここにいてくださいましたら、わたしの兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお願いになることは何でも神はかなえてくださると、わたしは今でも承知しています。」~この言葉は何を意味しているのでしょうか。
初めの言葉、「主よ、もしここにいてくださいましたら、わたしの兄弟は死ななかったでしょうに。」は、マルタは、イエス様が奇跡をおこない、人の病を治せるお方だと信じていました。真っ先に来てくれたなら、病を治すことができたかもしれない。まだ、息を引き取って間もない時なら蘇生したかもしれない。しかし、イエス様の超越的な力を持ってしも、4日経ってしまったのでは難しい。肝心の時にいなければ、何の役にも立たないと、不平を言っているのかもしれません。しかし、次に続くマルタの言葉は、「しかし、あなたが神にお願いになることは何でも神はかなえてくださると、わたしは今でも承知しています。」です。この言葉は、前の言葉と少し矛盾しているように聞こえます。この言葉通りに信じているのなら、前の言葉のような不満はでてくることはないはずです。
また次のやり取り、「あなたの兄弟は復活する」というイエス様の言葉に対して、マルタは、「終わりの日の復活の時に復活することは信じております。」と言っています。マルタの言った「終わりの日の復活の時に復活すること」とは当時のユダヤ教のファリサイ派が中心に信じていたことですが、「終末」と呼ばれているこの世の終わりが来るときに、死んだ人もよみがえり、生きている人とともに裁かれると考えられていました。マルタはこの考えを信じたのです。しかし、このことは、イエス様が言われた「あなたの兄弟は復活する」という言葉とはずれていたのです。
マルタはイエス様を特別な方であると感じていましたが、イエス様をメシアだとは、はっきり確信していなかったのです。そこでイエス様は、次の言葉、「わたしは復活であり、命である、わたしを信じる者はだれも、決して死ぬことはない。」で、イエス様自身が人々の考えを超越した存在であることを示し、マルタにせまります。この言葉を受けてマルタは、「はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであるとわたしは信じております。」
と答えます。マルタはここでイエス様が「メシア」であることを告白するに至ります。「メシア」とは、単に特別な力を持った人ではなく、「神の子」であるということです。
3.ともに苦しむ神様とイエス様
さて、創世記3章で「カインとアベル」の物語が描かれています。カインとアベルは楽園を追放されたアダムとエバの息子です。「アベル」と言う名前はヘブル語で「はかない」という意味を持ちます。神様はこのアベルの差し出した献げ物に「目を留められた」とあります。これは楽園を追放された人間とその子孫たちが「はかない」人生を地上で過ごしていくことに心を砕いていたからです。仏教では「四苦八苦」と言いますが、人間は生まれてから誰しも人生の「生・病・老・死」の苦しみは避けられないのです。誰もどうにもならないのです。神様はこの人間のはかない人生に心を痛めていたのです。そして、神の子であるイエス様もそうでした。イエス様はこの後、ラザロを生き返らせるのですが、マルタやマリアに、「生き返らせてあげるから悲しむ必要はないよ」とは言いませんでした。35節では、「イエスは涙を流された」とあります。また、38節では「心に憤りを覚えて」とあります。イエス様は、何に、「涙を流し、」「憤りを覚え」たのか。それは、人間のはかない運命についてです。ラザロだけではなくマリアやマルタだって人生の苦難の末、苦しんで死んでいくという運命を背負わされています。この人間のさだめについてイエス様は涙を流し、憤ったのです。たとえラザロが生き返ったとして、再び死ぬことは避けられません。本当の「永遠の命」にあずかるには、イエス様をメシアと信じる信仰が必要なのです。イエス様がラザロを生き返らせる理由は42節以降あかされます。「しかし、わたしがこう言うのは、周りにいる群衆のためです。あなたがわたしをお遣わしになったことを、彼らに信じさせるためです。」
と言ってから、「ラザロ、出て来なさい」と大声で叫ばれたのです。
4.わたしたちを愛し、永遠の命を与える方
現在わたしたちが直面している苦難があります。戦争や自然災害のように多くの人に共通することもあれば、個人的な悩みや悲しみもあります。そんなときに、一緒に重荷を担い支えてくれる家族や仲間がいることは大変心強いことです。何気ない一言で救われることもあります。ともに喜び、ともに泣いてくれる人がいるからこそ人間は生きられるのではないか、と思うのです。イエス様はそのような方です。復活された後も私たちと共にいて重荷を共に、になってくださっています。しかし、イエス様はそれだけではありません。メシアとしてわたしたちに永遠の命を授けてくださるのです。わたしたちが死んだのちも神様が支配する御国にわたしたちを迎えてくださるのです。このことが「わたしを信じる者は、死んでも生きる」という意味なのです。イエス様は一人の人間としてこの世を生き、人々とともに喜び、ともに泣いてくださった、このことが表しているのは、人間はともに生きることによって本当の生を生きることができるということです。しかもメシアであるイエス様は、神様の御国でわたしたちに安らぎと慰めを与えてくださるのです。このことを信じて希望を持ちたいのです。この信仰を強めていただけるよう祈りつつこの週も歩みましょう。
神様
今日もみ言葉をありがとうございました。
本日はヨハネ福音書11章より、イエス様の力強い言葉
「わたしを信じる者は、死んでも生きる」を聞きました。
どうか憐れみをもって、信仰の弱いわたしたちを強めてください。どうか主イエスの復活の命にあずかることができますように。