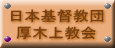
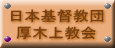
1.これらのこと
本日の聖書のテキスト25節の後半、
「これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。」とあります。「これらのこと」とは、イエス様が人間を救うメシアであるということです。メシアとは、人間を罪の鎖から解放してくださる救い主を指す言葉です。つまり、「これらのこと」とは一言でいえば、「福音」を指すのです。
しかしながら、イエス様がメシアであるという「福音」は、簡単には受け入れることができないことです。
使徒言行録17章の16節以降には、パウロが第2回宣教旅行でギリシャのアテネという都市に行った時のことが記されています。パウロはそこのアレオパゴスという丘に立ち、アテネ市民に福音のことを力強く説教しました。
「アテネの皆さん、あらゆる点においてあなたがたが信仰のあつい方であることを、わたしは認めます。道を歩きながら、あなたがたが拝むいろいろなものを見ていると、『知られざる神に』と刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それで、あなたがたが知らずに拝んでいるもの、それをわたしはお知らせしましょう。世界とその中の万物とを造られた神が、その方です。この神は天地の主ですから、手で造った神殿などにはお住みになりません。また、何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息と、その他すべてのものを与えてくださるのは、この神だからです。神は、一人の人からすべての民族を造り出して、地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは、人に神を求めさせるためあり、また、彼らが探し求めさえすれば、神を見いだすことができるようにということなのです。実際、神はわたしたち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちのある詩人たちも、『我らは神の中に生き、動き、存在する』『我らもその子孫である』と言っているとおりです。わたしたちは神の子孫なのですから、神である方を、人間の業や考えで造った金、銀、石などの像と同じものと考えてはなりません。」
さて、神はこのような無知な時代を、大目に見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと、命じておられます。それは、先にお選びになった一人の方によって、この世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。」
この後の32-33節には、それを聞いたアテネ市民の反応が書かれています。
「死者の復活ということを聞くと、ある者はあざ笑い、ある者は、『それについては、いずれまた聞かせてもらうことにしょう』と言った。」
と書かれています。ギリシャはプラトンやアリストテレスといった哲学者が有名であり、パウロの説教を聞いていた人々は、ギリシャ哲学のエピクロス派とストア派の人々であったと考えられています。エピクロス派は「宇宙を原子と空間による機械論で説明し、感覚主義的快楽説をとる」。いっぽうストア派は「唯物論的・汎神論的・倫理的立場をとる」、ということです。わたしもよくわかりません。ギリシャ人は、頭が良い人々で、よく物事を考えて、思想を形成する事には興味を示しました。しかし、十字架につけられたイエス様のことにはぴんとこなかったようでした。それは、十字架のことは、頭で考えても理解をすることができないからです。このように、頭の良いというだけでは、人は福音の事柄を受け入れられません。
ギリシャのアテネで、そのような体験をしたパウロは、同じギリシャにありますコリントの教会に手紙を出しています。コリントの信徒への手紙一の1章18節(p300)で、「十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、わたしたち救われる者には神の力です」と言っています。「十字架の言葉」とは、イエス様の十字架によって救われるという言葉です。「十字架」というのは、もともと嫌なものです。犯罪人の死刑方法です。普通の人は、神様の子が十字架にかけられる意味が理解できません。神様だったら、そんな痛い思いをしなくても、もっといい方法があるだろうと考えるのです。多くの人にとっては「十字架の言葉」は「愚かなもの」、ばかばかしいものなのです。
2.幼子とは
ここで、マタイ11章25節に戻りますが、「知恵ある者や賢い者」に対して「幼子のような者」を反対側にいる者としてとらえています。「幼子のような者」とはどのような者なのでしょうか。
ここでいう「幼子」はギリシャ語で「ネーピオス」という言葉です。「ネー」は否定語です。「ピオス」は話すという意味です。つまり、「ネーピオス」とは、話すことができない人のことを指します。ですから話す以前の幼児を指しますし、あるいは、話す能力が無い人をさします。話すことのできない幼児というのは、どのような人でしょうか。
以前いた教会のこども園の0歳児のクラスは、まだ言葉がない子どもたちがたくさんいます。言葉がないからといって知恵がないかというと、そうではなく、言葉が無くても、大きな声で泣いて意思を伝えます。言葉がないからといって、侮ることはできません。ですから、ここで言われている「幼子」とは、言葉を持たないということだけでなく、「知識」や「思想」というものにおいてまだまっさらで、はじめて見るものを受け入れることができる者と考えることができます。こども園の子どもの多くは、神様がいると信じてくれて一生懸命お祈りをしました。これは、子どもたちは無垢だからだまされやすい、ということではないと思います。まっさらな気持ちをもっている人間には神様がともにいらっしゃることが、直観的にわかるのだと思います。人間が成長して世の中のことを知ったり、様々な知識や思想をもっていくと、神様を感ずる感覚がにぶくなってきてしまうと思うのです。ユーミンの「やさしさに包まれたなら」という曲があります。この歌の歌詞が「小さい頃は神様がいて、毎日愛を届けてくれた」とあります。おそらくユーミンも、幼いころは神様を信じることができたけれども、大きくなるに従ってその心を失ってしまったという感覚を歌っているのだと思います。イエス様は、「知恵ある者や賢い者」には福音が隠されており、「幼子のような者」には示されたと言います。いったん「知恵ある者や賢い者」になってしまうと、イエス様がメシアだという福音を聞いてもとりあわないのです。「知恵ある者や賢い者」は、様々な知恵や力に邪魔されて、福音を受け入れることができません。自分がもっている能力をもって、必要なものは手に入れる。だから、福音は「間に合っています」というのです。
わたしの子どもたちの世代も、情報が豊富です。「いかに資産を増やすことができるか」、「いかに上手に人と付き合うか」、「いかに快適に過ごすことができるのか」、こういったノウハウには敏感です。「タイパ(タイムパフォーマンス)」などと言って、ものごとを合理的に進めることにたけています。知識が頭の中を一杯にしているので人間を超越する存在が入る余地がありません。それに対して「幼子のような者」は、余計なものをもっていないので、「間に合っています」ということができません。福音を聞いて、それを素直に受け入れることができるのです。
3.示そうとする
次に27節を見ます。
「すべてのことは、父からわたしに任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と、子が示そうと思う者のほかには、父を知る者はいません。」
「幼子のような者」であるわたしたちは、たまたまイエス・キリストを受け入れたのではありません。実は、わたしたちがそう考える前に、イエス様が「示そうと思」ったというのです。今、この礼拝に出席されている方が30人ほどいらっしゃるのですが、厚木市には20万人からの人が住んでいます。他の教会に出席されている方もいますが、全部足しても100人に満たないでしょう。100人にひとり以下の確率です。
さらに言えば礼拝に出席されている皆さんは、今日は暇だからたまたま出席したとわけではありません。この日の礼拝に備えてこられた。それは皆さんが、イエス様が福音を「示そうと思っ」た方々であり、そのイエス様のお招きに皆さんが応えたということです。
4.軛(くびき)を負う
最後に28-30節です。
このみ言葉は、有名な言葉であり、イエス様の招きの言葉であります。
「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。わたしは柔和で謙遜な者だから、わたしの軛を負い、わたしに学びなさい。そうすれば、あなたがたは安らぎを得られる。わたしの軛は負いやすく、わたしの荷は軽いからである。」
軛というのは牛など、家畜が首にはめる板のことをいいます。ある場合には、2頭の牛がひとつの軛をはめられて、車を引かせられたりします。わたしたち人間はだれでも軛をはめられて、わたしたちの主人の荷物を引かせられている存在であるといってもいいでしょう。
現代では「ブラック企業」という言葉が定着しており、人々が仕事を選ぶのも随分慎重になりました。求人をすると、「年休の消化率はどのくらいなの?」「残業はあるの?」「職員の定着率は高いの?」と聞かれます。仕事の内容は聞かなくてもいいのかな、と思うくらいです。過労死が深刻な時代ですから、仕事の労働条件が大切だということでしょう。
わたしたちが負う軛は、わたしたちが誰を主人にするかで、その荷の重さが変わってくるのです。わたしたちは知らず知らずのうちにとんでもない重い荷物を背負っていることがあります。そのためにへとへとに疲れて、倒れそうになっているかもしれません。
しかし、イエス様を主人とすれば、イエス様の軛は負いやすく、荷物は軽いと言います。それは、イエス様は柔和で謙遜なものだからと言います。イエス様は人間のために十字架にかかられたのですから、イエス様ほど柔和で謙遜な方はおられないと思います。イエス様の軛とはどんなものでしょうか。自分中心ではなく、相手の立場になって考える。神様の愛とゆるしのうちを生きるということでしょうか。殺伐とした社会の中で、イエス様の軛を負うことは容易でないかもしれません。しかし、わたしたちひとりひとりが神様にとってかけがえのない存在であること、決して世の中の使い捨ての歯車ではないことを心に刻みたいと思います。
神様はわたしたちにイエス様のことを示そうと選んでくださり、「幼子のような者」のこころを与え、そしてさらに、負いやすい軛に取り換えてくださるのです。イエス様を信頼して、すべてをゆだねて、この週も歩んでまいりたいと思います。