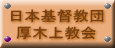
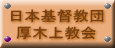
1.新しい掟
さて、本日の聖書のテキストはエゼキエル書18章です。エゼキエルは第一次バビロン捕囚でバビロンに連行され、異国の地で預言をすることになった異例の預言者です。この第一次バビロン捕囚は、南ユダ王国が滅亡することになったいわゆる「バビロン捕囚」の10年前におこりました。第一次の捕囚ではヨヤキン王と軍人など一部の人たちがバビロンに連れていかれるのですが、それでもイエスラエルの人々は楽観的でした。そのうち人質も返してもらえるだろうと考えていたのです。それに対してエゼキエルはただちに悔い改めなければ南ユダ王国が滅亡すると預言しました。今日のテキストが含まれる18章では、エゼキエルが、「各人の責任」という、旧約聖書の中ではかなり画期的だと思われることを言っています。18章の5節から13節を読みます。
「もし、ある人が正しく、正義と恵みの業を行うなら、すなわち、山の上で偶像の供え物を食べず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を犯さず、生理中の女性に近づかず、人を抑圧せず、負債者の質物を返し、力ずくで奪わず、飢えた者に自分のパンを与え、裸の者に衣服を着せ、利息を天引きして金を貸さず、高利を取らず、不正から手を引き、人と人との間を真実に裁き、わたしの掟に従って歩み、わたしの裁きを忠実に守るなら、彼こそ正しい人で、彼は必ず生きる、と主なる神は言われる。
彼に生まれた息子が乱暴者で、これらのことの一つでも行う人の血を流し、自分自身はこれらすべての事の一つですら行わず、かえって山の上で偶像の供え物を食べ、隣人の妻を犯し、貧しい者、乏しい者を抑圧し、力ずくで奪い、質物を返さず、偶像を仰ぎ見て忌まわしいことを行い、利息を天引きして金を貸し、高利を取るならば、彼は生きることができようか。彼は生きることはできない。彼はこれらの忌まわしいことをしたのだから、必ず死ぬ。その死の責任は彼にある。」(5-13節)
ここで言われているのは、神様と交わした契約を守ることの大切さです。わたしたちは、「律法」と聞くと意味のない形式主義と思いがちですが、もともと「神様の掟」は、神様をとおして示された正義と憐れみをまっとうすることでした。そして、そうする者は最後には「必ず生きる」と言われています。そしてさらにエゼキエルは、正しい人の子がまったく親とは逆で、神様の掟をまるで守らないという場合は「生きることはできない」と言います。この場合の「生きる」とは、わたしたちにとっては、神様と共に歩むことができる、という意味です。それはわたしたちが、神様と共に歩む人生こそ本当の意味で自分自身の人生をまっとうすることだと考えているからです。
さて、先ほどこの箇所で画期的なことが言われていると申し上げましたが、どこが画期的かと言いますと、それまでのイスラエルの伝統的な考え方は、旧約聖書申命記5章9節には「わたしをいなむ者には、父祖の罪を子孫に3代、4代までも問う」と、先祖の罪が子孫に及ぶと書かれており、人々の間ではこの考え方が支配的でありました。これに対してエゼキエルは、神様の方針転換とも思われる預言をします。それは18章の2節に書かれてあることです。
「お前たちがイスラエルの地で、このことわざを繰り返し口にしているのはどういうことか。
『先祖が酢いぶどうを食べれば/子孫の歯が浮く』と。
わたしは生きている、と主なる神は言われる。お前たちはイスラエルにおいて、このことわざを二度と口にすることはない。すべての命はわたしのものである。父の命も子の命も、同様にわたしのものである。罪を犯した者、その人が死ぬ。」
すっぱいぶどうを食べれば、「歯が浮く」というのは、口の中がしびれる、ということでしょうか。食べた本人がそのような目にあうのは当たり前ですが、その症状が子孫に生じるというのです。これは、先祖の犯した罪が子や孫にたたる、ということです。それに対して、エゼキエルは、これからはもう違います、というのです。その本人が正しければ、その人は神様によって報いられるが、そうでなければ、罰せられるということです。親がどんなに偉い人であっても、子ども本人が悪ければ、その本人が責任を追及されるのです。親の七光りで、子どもの罪を見逃すといったことは許さない。また逆に親がどんなに悪くても、子どもが正しければ、まったく影響されない。本人次第であると、エゼキエルはいうのです。
2.立ち返ることを待つ神様
さて、エゼキエルはなぜ、このようなことを預言したのでしょうか。25節を読みます。
「それなのにお前たちは、『主の道は正しくない』と言う。聞け、イスラエルの家よ。わたしの道が正しくないのか、正しくないのは、お前たちの道ではないのか。」
エゼキエルの預言の中心は「悔い改め」でした。前代未聞の国難に際して、あなた方自身が悔い改めなさいというのです。このことを聞いて、イスラエルの人々は反抗します。「主の道は正しくない」と言うのです。「主の道は正しくない」というのは、「神様は間違っている。」と言う意味です。イスラエルの人々は、現在苦しい状況におかれているのは、先祖の罪のせいで自分たちは間違っていない。自分たちに悔い改めを迫るのはお門違いだと訴えるのです。それに対して、神様は、勘違いするな、イスラエルの苦難は先祖の罪でなく、あなたたち自身の罪のせいであると断言するのです。しかし、それでも神様はご自身のあわれみから、人々が滅びることをよしとはなさいませんでした。神様に立ち帰ることをせつに求めるのです。
そして次に神様は、個人が過去のおこないにとらわれずに、その人のこれからのことで判断されるというお考えを明らかにします。
(21-23節)
「悪人であっても、もし犯したすべての過ちから離れて、わたしの掟をことごとく守り、正義と恵みの業を行うなら、必ず生きる。死ぬことはない。彼の行ったすべての背きは思い起こされることなく、行った正義のゆえに生きる。わたしは悪人の死を喜ぶだろうか、と主なる神は言われる。」
神様の掟に従うとは、神様の正義と恵みの業を行うことを意味しました。これに対してイスラエルの人々は、神殿の祭司でさえも異教の神をあがめて自己中心的なおこないをやめませんでした。神様に頼らず、外交面ではエジプトに援助を求めてバビロンに対抗しようとしました。こうした反抗的な人々に対しても神様は救いたいと考えます。悔い改めて、生きてほしい、と訴えるのです。もし、悪を行ってしまった人であっても、悔い改めて、正義と恵みの業を行うなら、今までのことはすべて不問に付すというのです。そして、再び、神様とともに歩むことができる、と言って下さるのです。逆に、今までどんなに善行を積んできたとしても、この瞬間に正しさから離れるのなら、これまでのことはすべて台無しになってしまうのです。つまり、わたしたちが本当に神様と共に歩むことができるかどうかは、今この瞬間わたしたち自身の決断にかかっているということです。
3.私たちの十字架
さて、翻ってわたしたちの信仰について考えたいと思います。わたしたちは、それまで自分の好きなものをおがんでいましたが今は悔い改めて主イエス・キリストを与えてくださった父なる神様への信仰にしたがって歩んでいます。この信仰によって既にわたしたちは赦されているのですが、この恵みへの応答としてわたしたちには新しい掟が与えられていいます。それは、イエス様の言われた「お互いに愛し合う」、「お互いに許しあう」ことです。これがわたしたちの負うべきわたしたちの十字架です。そしてさらに言えば、「お互いに愛しあう」、「お互いに許しあう」というのは「言うが易し行うが難し」で実際には難しいことです。それでも神様は辛抱強くわたしたちが変わっていくことを待ってくれています。
23節「わたしは悪人の死を喜ぶだろうか、と主なる神は言われる。彼がその道から立ち帰ることによって、生きることを喜ばないだろうか。」わたしたちが悔い改めるのを辛抱強く待っている神様に感謝し、聖霊の働きを求めつつ歩みたいと思います。